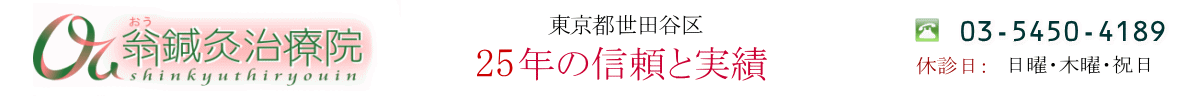顔面麻痺の治療例と注意点
顔面神経麻痺の関連コンテンツ
- 顔面神経麻痺の鍼灸施術について
- 顔面麻痺評価法と障害部位について
- 顔面麻痺の治療例と注意点について
- 鍼灸治療に関するご相談やご質問
当院の鍼灸治療の症例
次にいくつかのを挙げてみます。
(1)N・Hさん 34歳 男性 ベル麻痺 総合病院で顔面神経麻痺と診断され、ステロイド剤を出された。主訴は「うがいができない」「目が完全に閉じない」。発症10日後に来院。顔面運動評価などテストして顔面神経は不完全麻痺とされる。3週間後に海外出張することになるため、ご本人の希望もあって、一週間に四回の集中的な鍼灸治療を行った。二週間後に麻痺が完全に取れていた。3週後は少し違和感が残っているものの、後遺症を残さず完治した。この方は完全麻痺ではないということも早期回復の要因の一つと思われる。早期の鍼灸と短期集中的な治療もよい効果をもたらすと考えられる。
(2)M・Nさん 35歳 女性 ハント症候群 発症してすぐ入院しステロイド点滴、抗ウィルス剤服用、神経ブロックを受けるがあまり芳しくなく医師に手術を勧められる。顔の左半分マヒ、味覚も感じないところがあり耳が痛い。当初は入院しながら週2回のペースで通院し、退院してからも週2~3回通う。1回ごとの治療では明らかな変化は認められないが、3ヶ月、4ヶ月と経過を見ると徐々に回復が認められるようになり、7~8ヶ月目になると外見上ほとんど顔面マヒだと判らないくらいまで改善する。その後も少しこわばりを感じたり調子があまり良くないときに不定期に鍼灸を受けに来る。勧められた手術を受けずに鍼灸でよくなったことで本人も胸をなでおろしている模様で、予想以上の好結果が得られた。
(3)O・Mさん 49歳 男性 ベル麻痺 病院で1週間ステロイド点滴、その後ビタミン剤服用を続ける。 発症後一週間後に来院。初診での主訴は「口の周りから水が漏れる」 顔を正中腺(中心を通る線)で分けて見ると唇は右側へ引っ張られ、鼻唇溝も非対称となる。額をつり上げるマッサージをするとまぶたもつられて開き、白目が露出する。週に2~3回の治療を受け、3ヶ月ほど経つと顔の印象が整ってきて水も漏れなくなり、白目が露出することがなくなった。また自覚症状としてのこわばりは日を追うごとに改善しているようだが、マッサージをする側からもこわばりが取れていくのがわかった。発症して初診までの2ヶ月弱は全く変化が見られなかったが、治癒をあせらず鍼灸を受け続けたのがよかったと思われる。
(4)E・Tさん 31歳 男性 ベル麻痺 発症の2日後で顔の左半分が完全麻痺、こわばっている感じる。頭痛を伴う。病院ではステロイド点滴と漢方を処方される。二週間後に来院。1回目で頭痛が取れ、こわばりが少しやわらかくなる。1週間に3回のペースで通院し1ヶ月経つと、見た目には分からないくらいまで回復。よく観察すると口を広げるときに左側が少し広がりきらない感じはあるが機能的には問題ない様子。その後は週に1回で何回か通院していて、後遺症を残さずに完治できた。傷害された部位が深くなかったことと発症後すぐに来院したことで、効果的な治療ができ比較的早い回復がみられた。
(5)M・Y さん 20歳 男性 ハント症候群 主訴は「表情が出せない」。発症から5ヶ月ほど経過してからの来院。1回目の治療後、自覚的に顔のこわばりが少し取れた模様。仕事の都合でコンスタントに通院できないが週に1~2回のペースで治療を受け、しばらくすると顔の筋肉に柔軟性が出てくる。異動で東京を離れるまで3ヶ月ほど通い、完全ではないがそれまで自分で思うように作れなかった表情が作れるようになる。治療開始時期が遅く、初診の印象で回復は難しいように思われたが、本人の治りたい気持ちも手伝ってか鍼灸の効果が良く表れた。
顔面神経の完全麻痺期及び回復期における注意点
Ⅰ低周波(電気鍼)を避ける
低周波(電気)は麻痺側の筋肉を収縮させることによって、回復期では顔面神経核の興奮性が亢進しているために共同運動が出現しやすくなり、顔面拘縮の誘因になることもあります。長い間の鍼灸臨床経験と低周波刺激は禁忌という専門家の意見に基づいて、当院は回復期の顔面麻痺に低周波を使っていません。
Ⅱ顔面神経麻痺のマッサージについて
マッサージは麻痺した顔面筋肉の走行に沿って気持ちのよい強さでけっこうです。または蒸しタオルを使うと、顔面のこわばりに対して効果があります。マッサージ前に使って顔面筋のストレッチングを促します。
Ⅲ粗大筋力訓練は避ける
顔面神経麻痺になって麻痺側の筋力(表情筋)が低下したからと言って、荒っぽく強すぎる筋力訓練をすると中枢レベルの共同運動(後遺症)を誘導しやすなくなります。時間の経過とともに麻痺した筋肉の緊張は亢進し、顔面痙攣や顔面拘縮の誘因になります。
Ⅳ長時間に冷たい風を避ける
冷たい風やアイスを長時間顔面や耳の後ろ(顔面神経の出口)のあたりに当てると顔面神経麻痺になるかたもいます。顔面麻痺の側に冷たい風やアイスは避けたほうがいいです。特に回復期は要注意です。
Ⅴ顔面神経麻痺を治そうという気持ち
顔面神経麻痺になった原因はまだはっきりしないことが多いですが、超多忙の生活やストレスなどによって睡眠時間が極端に少なくなったり、また免疫力や体力が低下したことで麻痺になることも結構あります。できれば規則正しい習慣を身に付けて、自己健康管理をしっかりしましょう。免疫力や体力を高めて、治そうという気持ちを強くもち、常に前向き姿勢で臨むことによって、自然治癒力が高まり、麻痺の回復につながります。
顔面神経麻痺後遺症
顔面神経麻痺の予後は、障害の程度や範囲、病因、治療法、治療開始時期などによって様々です。臨床において最も頻度の高いBell(ベル麻痺)とRamsay hunt(ラムゼイ・ハント症候群)などの場合は、神経障害が軽度であれば、適度な治療によりほとんど後遺症を残さず回復しますが、神経障害が重度の場合はしばしば後遺症を残します。顔面神経麻痺の後遺症はさまざまありますが、主な後遺症は以下のようなものです。
①病的共同運動
病的共同運動は不随意運動と言われるもので、顔面神経麻痺の後遺症のなかで最も頻度の高い症状です。元々目のまばたきの筋肉に行く神経と、口の周囲の開け閉めに使う口輪筋は根っこは同じ顔面神経ですが、口の開閉に伴い目が動くという共同運動が起こる場合です。普通の場合は顔面麻痺の発症して3~4ヶ月ころから出現します。
②ワニの涙
食事に際して、多量の涙分泌されます。発症後数ヶ月経て出てくるものです。唾液腺へいく神経と涙腺にいく神経が誤って起きる現象です。「ワニの涙」とはワニは食べ物を食べると涙が出るのでこう言われます。
③顔面拘縮
患側の顔面が持続的に収縮した結果です。鼻唇溝は深く、眼裂は狭小化し、安静時も顔が非対称に見える状態を顔面拘縮といいます。原因は顔面神経の再生神経数が少ないと言われています。しばしば病的共同運動を合併しています。
④アブミ骨筋性耳鳴
表情筋を再生するはずの再生神経線維が誤ってアブミ骨筋を支配したために起こる現象です。目を閉じたリ、口を動かしたりとしたときにアブミ骨筋が収縮し、耳鳴や一過性難聴が生じます。
⑤顔面痙攣(けいれん)
麻痺側の顔全体に及ぶ痙攣が起こり場合と口と眼の周りに局所痙攣が起こる場合があります。症状はそれほど強くはありませんが、後遺症として残ることがあります。後遺症として顔面痙攣の原因はまだはっきりしていません。
完全麻痺期及び回復期における注意点
Ⅰ低周波(電気鍼)を避ける
低周波(電気)は麻痺側の筋肉を収縮させることによって、回復期では顔面神経核の興奮性が亢進しているために共同運動が出現しやすくなり、顔面拘縮の誘因になることもあります。長い間の鍼灸臨床経験と低周波刺激は禁忌という専門家の意見に基づいて、当院は回復期の顔面麻痺に低周波を使っていません。
Ⅱ顔面神経麻痺のマッサージについて
マッサージは麻痺した顔面筋肉の走行に沿って気持ちのよい強さでけっこうです。または蒸しタオルを使うと、顔面のこわばりに対して効果があります。マッサージ前に使って顔面筋のストレッチングを促します。
Ⅲ粗大筋力訓練は避ける
顔面神経麻痺になって麻痺側の筋力(表情筋)が低下したからと言って、荒っぽく強すぎる筋力訓練をすると中枢レベルの共同運動(後遺症)を誘導しやすなくなります。時間の経過とともに麻痺した筋肉の緊張は亢進し、顔面痙攣や顔面拘縮の誘因になります。
Ⅳ長時間に冷たい風を避ける
冷たい風やアイスを長時間顔面や耳の後ろ(顔面神経の出口)のあたりに当てると顔面神経麻痺になるかたもいます。顔面麻痺の側に冷たい風やアイスは避けたほうがいいです。特に回復期は要注意です。
Ⅴ顔面神経麻痺を治そうという気持ち
顔面神経麻痺になった原因はまだはっきりしないことが多いですが、超多忙の生活やストレスなどによって睡眠時間が極端に少なくなったり、また免疫力や体力が低下したことで麻痺になることも結構あります。できれば規則正しい習慣を身に付けて、自己健康管理をしっかりしましょう。免疫力や体力を高めて、治そうという気持ちを強くもち、常に前向き姿勢で臨むことによって、自然治癒力が高まり、麻痺の回復につながります。
家庭でできるリハビリ
マッサージについて
①上下の瞼の筋肉は人差し指と中指で小さい円を描くように伸張する。
②おでこは人指し指、中指、薬指で上下に走行して伸張する。
③口角と耳を結ぶ線上にある頬全体を上下、前後、人差し指、中指で小さい円を描くように伸張する。
④唇の周囲を円形に取り巻く部分を、人差し指、中指で円を描き、左右へも伸張する。
上眼瞼挙筋を使う
後遺症の病的共同運動として、食事のたびに眼が閉じてしまいがちになるので、発症の早期から上眼瞼挙筋(動眼神経に支配され、上眼瞼を挙げたり開眼したりする筋肉)を使って眼輪筋(目の周りの筋肉)伸張を行います。話すとき、食事のときに目を見開く練習をしましょう。
注意点とリハビリの方法
急性期のリハビリ
発症して1~2か月は急性期と言います。高度の神経障害の場合は発症4か月前後に後遺症が出てくることが多いので、経過を診ているうちにリハビリをして、少しでも早いうちに軽減できないものかと思います。急性期リハビリの目標は顔面神経の迷入再生による病的共同運動と顔面拘縮の予防と軽減です。
慢性期のリハビリ
4か月過ぎてもまだ完治していない場合は慢性期と言います。病的共同運動、顔面のこわばり、筋力低下、けいれんなど様々な症状がでてくることがあります。この時期は、表情筋は動き出している時期なので、強い随意運動を避けて、軽く局部を動かす随意運動がおすすめです。たとえば、口のまわりの筋肉を動かすときに、なるべくおでこや目の筋肉を動かさないとか、逆に、おでこを動かすときに目の筋肉を動かさないようにイメージ療法を取り入れてください。
回数、時間、期間について
1日: 朝・昼、夕の3回、1回あたり 10分くらい。温かいタオルで顔を温めてから行います。強力なマッサージは避けましょう。
顔面神経障害と予後・後遺症
1度の障害:
部分麻痺(不全麻痺)とも言います。神経が圧迫され、生理的に神経の伝導がブロックされて起こる麻痺です。顔面神経の外膜に圧迫されて凹んでいます。圧迫が解除されると伝導ブロックは解除されます。3~4週間前後の治療でほとんど完全回復します。
2度の障害:
長期にわたって神経が圧迫されて、解除されません。神経の静脈がうっ血になって、完全麻痺になっている場合が多いです。正しく治療してうまくいけば完全に回復しますが、そうでないと少し後遺症が残ります。治療は1か月から3か月間かかります。
3度の障害:
神経内圧の上昇がより長期間にわたり、神経の軸索が破損した状態です。
神経の損傷がつよいので、多少顔面神経麻痺後遺症が残ります。症状が強い場合は迷入再生から病的共同運動、筋力低下などの後遺症が現れることがあります。治療は3か月~6か月間かかります。
4度・5度の障害:
高度の障害。神経が断裂した時にみられます。4度はうまくいけば少し動き出せますが、後遺症が残ります。5度は自然治癒は望めません。神経移植など外科的処置が必要になります。